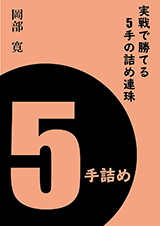詰連珠(五目のパズル)
連珠(五目並べ)の書籍
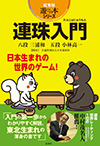


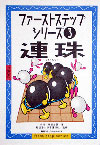
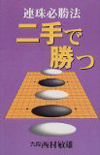

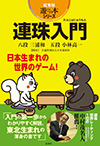
連珠入門 (遊びの本シリーズ)
基本のルールから分かりやすく徹底解説。さらに強くなる10のテクニック、ステップアップ講座、実力養成問題を掲載。
>> amazon
>> 楽天ブックス

新版 連珠必勝法
およそ50年にわたり読まれてきた連珠の基本定石集を大幅改訂。この1冊で、連珠の全珠型の打ち方の基本が分かります。
>> amazon
>> 楽天ブックス

中村シェフのおいしい詰連珠
詰連珠作品を新聞紙上でも数多く出題している中村茂帝王による作品集。短いながらも難易度が高く上級者向け。
>> amazon
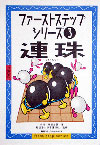
ファーストステップシリーズ(3) 連珠
「五目並べ」が発展した、世界的な卓上ゲーム「連珠(れんじゅ)」。本書はその連珠の基本の打ち方から、勝ち方までを詳しく解説しています。
>> amazon
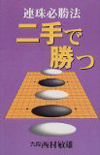
連珠必勝法「二手で勝つ」
連珠の基本定石といわれる初心者向きの珠型「花月」「浦月」「恒星」の必勝手順、さらに「桂馬打ち」の代表的な組立てと攻防の手順などを解説。また、黒の二手勝ちの問題を72題出題する。
>> amazon

これが連珠(ごもくならべ)だ
数多くの経験や実践記録をデータにして、まったくの初心者から可成りの棋力をもったベテランに至るまで役に立つであろうことを予測して編集。
>> amazon
連珠の用語
連や禁手に関するもの
- 「三(さん)」
- 三つの石が連なった状態で止まりのないものを三連、一箇所だけ石一つ分の間を開けて並んだ状態のものを飛び三といい、三連や飛び三のことを活三という。また、止まりのあるものを眠三といい、これは活三ではない。
- 「四(し・よん)」
- 四つの石が連なった状態で片側に止まりのあるものを四連、一箇所だけ石一つ分の間を開けて並んだ状態のものを飛び四という。また、両端に止まりのない四連のことを棒四や達四という。
- 「五連(ごれん)」
- 石が五つ並んだ状態。これを早く作った側の勝ちになる。
- 「三三(ささん)」
- 活三を同時に二つ以上つくること。黒がこれをすると禁手になるので、白にしかできない。
- 「四三(しさん)」
- 活三と四を同時につくること。
- 「四四(しし)」
- 四を同時に二つ以上つくること。 黒がこれをすると禁手になるので、後手にしかできない。
- 「禁手(きんて)」
- 黒が打つと負けになるもの(三々禁・四々禁・長連)。[参照]
- 「三三禁(さんさんきん)」
- 黒が活三を同時に二つ以上つくること。禁手とみなされて負けになる。
- 「四四禁(よんよんきん・ししきん)」
- 黒が四を同時に二つ以上つくること。禁手とみなされて負けになる。
- 「長連(ちょうれん)」
- 六つ以上の石が連なった状態。黒が打つと禁手、白が打つと五連とみなされる。
基本的なもの
- 「先手(せんて)」
- 黒石を用いて先に打ち出す側。黒ともいう。
- 「後手(ごて)」
- 白石を用いて迎え討つ側。白ともいう。
- 「仮先(かりせん)」
- 二題打ちで、珠型を提示する側。[参照]
- 「仮後(かりご)」
- 二題打ちで、珠型を選択する側。[参照]
- 「握り(にぎり)」
- 仮先と仮後を決めるときの方法のひとつ。互いに石を握り、その数で決める。[参照]
- 「天元(てんげん)」
- 盤の中央のこと。
- 「盤端(ばんたん)」
- 盤の端のこと。
- 「基本珠型(しゅけい)」
- 三手までの定められた型のこと。珠型ともいう。[参照]
- 「直接打ち(ちょくせつうち)」
- 白二手目を、黒一手目の縦(横)に付けること。直接ともいう。[参照]
- 「間接打ち(かんせつうち)」
- 白二手目を、黒一手目の斜め隣に付けること。間接ともいう。[参照]
- 「筋(すじ)」
- 五連に至るまでの道筋。[参照]
- 「組立て(くみたて)」
- 石を配置して筋をつくること。勝つための布石。
- 「定石(じょうせき)」
- 最善とされている手立て。[参照]
- 「慣手(かんしゅ)」
- その局面において、定石の次に強いとされる次善の手。
- 「変化(へんか)」
- 防ぎの場所を変えて、相手を未知の局面へと誘うこと。
- 「正着(せいちゃく)」
- その局面において、正しいとされる着手。
- 「異着(いちゃく)」
- その局面において、正着ではないとされる着手。
- 「絶対(ぜったい)」
- そこにしか打てない状態。
- 「強防(きょうぼう)」
- その局面において、強いとされている防ぎ。
- 「満局(まんきょく)」
- 引き分けのこと。
動的なもの
- 「追う(おう)」
- 攻めること。追い手のこと。
- 「引く(ひく)」
- 三(活三)をつくること。
- 「伸びる(のびる)」
- 四連を作ること。
- 「見せる(みせる)」
- 放っておくと四三になる手を打つこと。見せ手のこと。[参照]
- 「含む(ふくむ)」
- それ以降が、四追いで勝ちに至る手を打つこと。
- 「狙う(ねらう)」
- 禁手に極めて勝とうとすること。
- 「極める(きめる)」
- 黒に禁手を打たせて勝つこと。嵌めるとも言う。極め手のこと。[参照]
- 「逃げる(にげる)」
- 禁手から逃れようとすること。
- 「止める(とめる)」
- 相手の連や筋をさえぎること。[参照]
- 「飛ぶ(とぶ)」
- 飛び三や飛び四を打つこと。石一つ分、間を開けて打つこと。
- 「乗る(のる)」
- 相手の追いを防ぎながら、こちらの追いとなる手。乗り手のこと。[参照]
- 「割る(わる)」
- 石と石の間に入り込み、相手の展開をさえぎること。
- 「呼ぶ(よぶ)」
- 直接的な追い手とならない、組立ての為の布石。呼珠を打つこと。休むともいう。呼び手のこと。
- 「叩く(たたく)」
- 相手の有効な連を、脅威にならないうちに止めておくこと。
- 「捌く(さばく)」
- 相手の筋を切り崩し、自分の筋を組立てること。
技巧に関するもの
- 「外止め(そとどめ)」
- 飛び三を、中へ割って入らず外側で止めること。[参照]
- 「夏止め(なつどめ)」
- 三連の両端ともを一目開け、接しない状態で止めること。[参照]
- 「透かし止め(すかしどめ)」
- 相手の二連を一目開けて接しない状態で止め、脅威となる方向へと展開できなくすること。[参照]
- 「牽制(けんせい)」
- 自分の筋を使って相手の筋を止めること。[参照]
- 「両見せ(りょうみせ)」
- 一手で同時に二ヵ所を見せること。[参照]
- 「両勝ち(りょうがち)」
- 一手で同時に二ヵ所の含みをつくること。
- 「桂馬の網(けいまのあみ)」
- 連続した桂馬で網のような状態をつくり、相手の動きを封じる技。 [参照]
- 「四追い(しおい)」
- 連続した四で追うこと。[参照]
- 「四先(しさき)」
- 相手に追いがある時、四を巧みに用いて難を切り抜けること。
- 「解禁(かいきん)」
- 禁手の焦点(=禁点)を開放すること。[参照]
- 「六腐(ろっぷ)」
- 長連筋になり、筋が使えない状態。腐るともいう。[参照]
- 「呼珠(こしゅ)」
- 呼び手を打つこと。