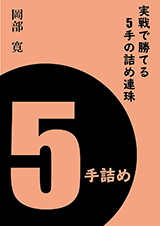詰連珠(五目のパズル)
連珠(五目並べ)の書籍
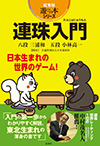


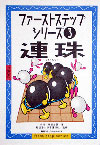
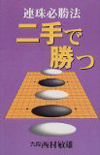

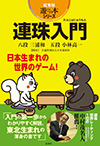
連珠入門 (遊びの本シリーズ)
基本のルールから分かりやすく徹底解説。さらに強くなる10のテクニック、ステップアップ講座、実力養成問題を掲載。
>> amazon
>> 楽天ブックス

新版 連珠必勝法
およそ50年にわたり読まれてきた連珠の基本定石集を大幅改訂。この1冊で、連珠の全珠型の打ち方の基本が分かります。
>> amazon
>> 楽天ブックス

中村シェフのおいしい詰連珠
詰連珠作品を新聞紙上でも数多く出題している中村茂帝王による作品集。短いながらも難易度が高く上級者向け。
>> amazon
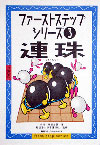
ファーストステップシリーズ(3) 連珠
「五目並べ」が発展した、世界的な卓上ゲーム「連珠(れんじゅ)」。本書はその連珠の基本の打ち方から、勝ち方までを詳しく解説しています。
>> amazon
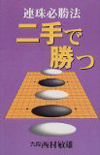
連珠必勝法「二手で勝つ」
連珠の基本定石といわれる初心者向きの珠型「花月」「浦月」「恒星」の必勝手順、さらに「桂馬打ち」の代表的な組立てと攻防の手順などを解説。また、黒の二手勝ちの問題を72題出題する。
>> amazon

これが連珠(ごもくならべ)だ
数多くの経験や実践記録をデータにして、まったくの初心者から可成りの棋力をもったベテランに至るまで役に立つであろうことを予測して編集。
>> amazon
連珠の格言
過去にWEBから集めたものです
- 「引いた方へ止めよ」
- 相手が三を作ってきた時、三を作ってきた側を止めるのが良いということ。逆側を止めるのが良い場合もありますが、展開したい方向に三を作ってくる事が多いからです。
- 「四伸びは勝ちを消す」
- 四のリーチは、むやみにしない方が良いです。先手は四三でしか勝てないので、四を作ってしまうと四三の芽がなくなってしまいます。四のリーチは、状況をよく見て必要なときに打ちましょう。
- 「引くに妙なく休むに妙あり」
- 三や四のリーチばかり打っていては、すぐ手詰まりになってしまいます。何手か先を考えて、自分の手がつながるように組んで行きましょう。
- 「盤は丸く打て」
- できるだけ外に広がるように心掛け、攻めるスペースを確保しましょう。スペースがなくなると、いろいろな方向に展開できなくなってしまいます。(密集させる作戦もありますが)v
- 「石を止めずに筋を止めよ」
- 単に連なっている石を止めるのではなくて、相手はどの様な手筋で展開できるのかを読み、その筋をさえぎるのが止めるという事。五つの石を並べるのが目標だけど、そこに至るまでは筋の読み合いです。
- 「敵の急所は我が急所」
- 攻める側も防ぐ側も相手に置かれたくない、勝負を左右する重要な場所。
- 「三剣あって勝てぬ事無し」
- 片側が止まっている三を剣(剣先・眠三)と言い、四連の一歩手前です。これがいくつかあると勝てる可能性が高いので、どの様につなげていけば良いか盤をじっくり見てみましょう。
- 「三三は四三の卵」
- 三三禁になる位置を白が放っておくと、黒は容易に見せ手(四三の手前)を作ることが出来ます。三三禁を利用する手もありますが、「四三が怖いので、いっそのこと三三禁もろとも止めてしまう手もあるよ」ということです。
- 「見せ手は勝ちを生む」
- 見せ手を打つメリットは、見せ手の焦点をオトリにして、別方向に展開できる点です。これはただ単に展開するだけではなく、自分が攻めていきたい方向以外の場所に、相手の石を追いやる事ができます。止められる場所が増えるというデメリットもありますが、とても使える技です。 また、見せ手を打たないと勝てない局面は多々あります。
- 「乗り手の一発形勢逆転」
- 追い込みに入っている状態でも、一つの石で逆転することがあります。「牽制の状態を見落とすと、痛い目に合いますよ♪」と、いうこと。 最後まで気が抜けません。
- 「定石は覚えてから忘れて打て」
- 定石を学ぶというのは、丸暗記することではありません。定石に詰まっている「勝つための考え方」を会得するということです。どんな局面でも最善の手を見極められるよう、定石に込められている考え方を、自分のものにできれば良いですね。
- 「白を持ったら禁手を狙え」
- 連珠(五目)は、先手に禁手があってこそ対等に楽しめます。後手が禁手を利用せずに勝つのはとても難しいことなので、ぜひ利用してください。
- 「攻めるは守るなり」
- 追うことばかりが攻めではなく、相手の手を封じる事が攻めにつながる事もあるということ。また、そのままの意味で「攻撃は最大の防御なり」という解釈もありました。